こんにちは、れもんです!
みなさんは自己肯定感には、良いものと悪いものの2種類に大別されることをご存知でしょうか?
おそらく、「今初めて聞いた」「良いものだけじゃないの」と思った方が少なくないと思います。自分も、読むまではそう思っていました。。
今回はそのような自己肯定感について、脳科学の観点から説明されている書籍をご紹介したいと思います。
大まかな内容
この書籍では、まず「いい自己肯定感」と「悪い自己肯定感」の2つを取り上げており、その差異について説明されています。
その後、前者の強みや「自己否定」を追い出す方法について触れられています。
4章以降では、「自己を肯定する基準のつくり方」「脳に自身が宿る週習慣」などと、実際に肯定感を身に着けるためのアウトプットする場が用意されています!
特長
この書籍の著者が「脳内科医」であるため、脳科学の視点から自己肯定感の本質に迫っている点が特長です。
脳にはそれぞれ役割に応じた「脳番地」があり、その脳番地と「自己肯定感の強み」「自己基準のつくり方」などを関連づけて説明されています。
印象に残ったこと

私はこの書籍を読んで、第1章の「『いい自己肯定感』と『悪い自己肯定感』がある」が印象に残りました。
なぜなら、「自己肯定感」という言葉を聞くと、自分を褒める。認める。といったポジティブなイメージがあったので、悪いのもあるという発見があったからです。
以下の文章が特に印象に残りました。
私たちは放っておけば、”自己否定”のループに陥ってしまう社会に生きています。
あるいは、一見、自己肯定感を持っているように感じても、そのじつは社会や世間の評価に基づいた「他律性自己肯定感」にすぎない可能性が高いのです。(中略)じつにもろいものです。
脳の名医が教えるすごい自己肯定感/加藤俊徳 p.64
著者は、「自律性自己肯定感」と「他律性自己肯定感」の2つがあると説明していました。
この後者を、引用部分では説明されています。
現代では、学生・社会人ともに社会的な尺度で測られる競争社会に生きています。偏差値・学歴によって評価をされたり、売り上げ、出世争いなど順位化をされたりと。
そのような社会に生きていると、自己理解よりも、社会の基準や他者の評価で自分を評価してしまう傾向があります。そうなると、劣等感を感じたり、攻撃的になったりします。
ですが、その後も、他者の評価で生きてしまうという負のループに陥るということですね。
そのため、他者軸の「他者認知」で生きるのはなく、自分軸の「自己認知」で生きることが大切だということです。
自己認知で生きていく

みなさんも、知らないうちに周りの人と比較して、劣等感を覚えた経験があるのではないでしょうか?
「自分は頭が悪い」「運動神経がない」などと。
劣等感が「見返したい」「頑張ろう」というようモチベーションに繋がる場合はいいのですが、そうではなく、自分を過度に否定しまったり、嫌いになってしまったりするのは問題です。
ただ、それはあなた自身が悪いのではなく、そうさせてしまう社会が問題なのです。その現状を知り、悪い方向に引っ張られないように、工夫して行動する必要があります。
その工夫が、自分と向き合い、自己理解を深める。そして、認めてあげることだと私は考えています。
この ”自分と向き合う” という部分が、
著者が取り上げていた自己認知を指しているのだと思います。
その後に、自分を認めてあげることで、簡単に揺るぐことのない「 ”自律性” 自己肯定感」が作り上げられていくのだと考えています。
そのため、自分を客観的に知る「自己認知」をすることが
自己肯定感を高めるためのはじめの第一歩になるのです。
まずは、自分と向き合うことから始めてみましょう!
おわりに
いかがでしたでしょうか。
私はこの書籍を読んで、他律性自己肯定感の存在を知り、「これからも自分と向き合っていきたい」「適度に脳に刺激を与えてあげたい」と思えました。
また、今まで感じていた、「他者と比較することの危険性」が他律性自己肯定感という言葉で、具体的に言語化されていたため、腑に落ちました。
科学的な視点、論理的な視点から、自己肯定感を高めていきたいと考える人にはお勧めの一冊だと思いました!
自己肯定感の低さに悩んでいる方は、よければ手に取ってみてください。


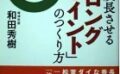


コメント